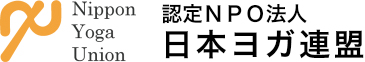お元気ですか?ココロとカラダ
受講生からの質問
<表示案内>
Q:受講生からの質問 / A:講師の回答 / 青字:ヨガアドバイザーからのコメント
2025.9.4追加
Q:清らかな欲とはどういう欲ですか(1日目)
A:
例えば知識を得たいとか、誰かの力になりたいなど。
でも誰かを助ける方法や度合いによっては、その方の機会や強くなれる力を奪ってしまう(アスティア)こともあるので注意も要ります。
※ヨガアドバイザーからのコメント
ご回答の通り、清らかな欲とは「あらゆるものを生かし、自利利他共にその喜びと感謝に満ちている生き方:心得」のことでしょう。
禁戒の教えは私達人間が最も陥りやすい「俗」で「邪」なる心模様を「汚れた不自然な欲」とし、生き方の浄化と人としての精神進化を説いています。
のちの段階のプラティヤハーラの土台となる教えとも言えるでしょう。
「清らかな欲」 もう少し深く説明すれば以下になります。
禁戒(社会全体・誰に対しても説かれている戒め)ですから、誰もが陥りやすい本能レベルでの説明を例とします
⇒自己の動物性を人として正しくコントロールし、精神的な成長を中心とした(神の意志にかなった)生き方をするため、それを超える能力を育てて生きる生き方を「清らかで自然な欲のままに生きる」という。
具体的には、邪欲になりやすい「食欲」を正しい知識や真理探究の欲へ転換したり、「性欲」をより正しい行動力へ転換するように努力するという沖ヨガの特徴:勧戒へ転換する生き方でより近づくことができる。
あらゆる場面で自分に与えられたものだけを戴く、運命をそのまま受けとり精神進化の糧にしていく、そのような心を育てる努力をすることが清らかな自然の欲(正欲)で生きることであり、その努力を継続することでこの戒めが知恵となっていきます。
Q:横文字が多くて覚えられるか不安、覚えなくてはいけませんか(1日目)
A:
テキストにも和名が表記してあるのでそれで頭に入れても良いです。
覚えることよりもその内容、本質を理解する方に重きを置いてください。
Q:先生は丹田は意識したらいつでも力を込める事が出来るのですか(1日目)
A:
日によって感覚の違いはありますが、練習で出来るようになっていきます。
Q:普段のレッスンでも修正法を指導しますか(4日目)
A:
行ないます。
ただ、そのクラスによってどういったかたちで展開するかは、受講者に沿ったものにする必要があります。
※ヨガアドバイザーからのコメント
ご存知修正法は沖ヨガ独自の考え方で「生き方としてのヨガ」の基本概念ですね。
矯正とは違うと言うこと。また身体の歪みにはなおしてはいけないものがあると言うこと即ち、生命の営みの邪魔をしている根底に潜むものに気づいて、その状態が自ら改善へ向かっていけるよう導引するのが修正法の基本概念です。
そしてそのやり方は呼吸が心身に与える影響力を活用し、身体に与えられている反作用力学を応用するものであったり、部分と全体の相似性理論を活用するものであったりと、沖ヨガにある実に豊かな考え方を受講生の皆様にはわかって頂けたようで、とても嬉しく思います。
Q:講師をする時に左右を逆にして、受けられている方と同じ方向で行う方がいいですか(5日目)
A:
同じように右なら自分も右を動かす先生のやり方もありますが、どちらかといえば、自分にとっては逆になるが、同じ方にした方が受けられている方にとってはわかりやすいかなと思います。
Q:仰向けになって動く時に顎を引くのはなぜですか(7日目)
A:
猫背の方や、顔が前に出ている方は仰向けで動いた時に顎が上がりやすくなって、首に負担がかかります。
その為、顎が上がっている方がおられたら引くように声をかけます。
Q:ラクダのポーズは、両手より片手で持つ方がやりにくく感じます(7日目)
A:
普段から肩が上がりやすいようなので、片腕を上げることで肩に力が入り、やりにくくなってしまうのではないかと思います。
Q:経絡促進氣功法を、ヨガの先生はレッスンでどの様に取り入れていますか(8日目)
A:
季節によって関連のある経絡の氣の流れを良くするような動きをすることもあります。
経絡や易しい東洋医学の話を交えることもあれば、あまり多く説明しすぎずにおこなうこともあります。
基点から終点までをさするだけのこともありますし、受講者の様子やそのクラスの目的に応じて取り入れています。
Q:呼吸の使い方がよくわからないです(7日目)
A:
アーサナのほとんどが、吐きながら動いています。(教科書参照)
吸いながらの動作は、コブラのポーズを実践しながら説明しました。
※ヨガアドバイザーからのコメント
呼吸をどうするか?ですが、確かに修正法はエネルギー変換の効率性を狙う事から、吐く息を用います。
しかしアーサナの呼吸の仕方は様々なようです。
例えば猫のポーズでは、我々(沖ヨガ)は、反屈のどちらも息を吐いて行いますが、他の団体では反る時に吸わせる指導もあるようです。実は、ご存知のようにどちらも間違いではありませんよね。
プラナヤマで学んだように、アーサナを行う時の呼吸の観察、それが引き出す状態の観察としてシャバアサナでの内観。
無理なく繰り返し続けていくことにより生命が自ずとより良い状態になるよう導いていく..
それがヨガですから、呼吸の仕方にも多様性があっで当たり前なのです。
受講生には、第二章プラナヤマで学ぶ「呼吸が心身に与える状態」の表を再度ご説明下さい。
そして、呼吸の仕方を固定化しないで活用する事が大切であることを教えてあげて下さい。
ヨガの十段階で言えば、プラティヤハラからダラーナ….
即ち、呼吸のコントロール力がその人の人生哲学を進化させていく段階です。
アーサナはその準備段階であることを是非お伝え頂きたいと思います。
Q:正座が出来ない場合はどうしたら良いですか(10日目)
A:無理にする必要はないが出来る様にしていく事も必要です。
→担当理事より
正座ができないというのは、ひざに痛みや怪我とか何らかの原因があるのでしょうか?
これは受講生ができないのか、それとも、今後クラスを行ったとき参加された中にできない方がいたら…ということなのか
十分気を付けて行っていただくよう、お伝えください。
Q:太陽礼拝で4点は必ずしないといけませんか(10日目)
A:必ずではありません。皆さんは指導者になるので4点も行いましたが、難しければ8点で構いません。
2025.3.28追加
Q:教室指導の際、右・左は特に言いいますか 言いませんか(5日目)
A:
受講者の理解度によりスムーズにいくなら言います。
大人数をひとりで指導するなら左右言うほうが混乱がないです。
ただし高齢者は左右とくに言わず行います。
Q:足がつった時の対応のしかたを教えてください(6日目)
A:
少しもみほぐして治るまで休んでもらいます。
また、アシスタントがいる場合はそばに行ってもらうが無理に伸ばすと危険なのでさするだけにし、声掛けでリラックスさせます。
Q:シッタリーとはなんですか(9日目)
A:
下を丸めて行う呼吸法で、暑いときに繰り返し行いクールダウンに役立ちます。
暑さが苦手なドーシャの対策として。
2024.5.23追加
Q:カルマ(業)をきれいにする方法は、その対象者へ実践しないと効果はありませんか(1日目)
A:
カルマの輪廻転生=因果応報の法則をお伝えしました。
ex.親孝行したい時には親はなしというが、親が生きていたらこのぐらいの年齢になっているだろうとして他のお祖母ちゃんに孝を行ずるのであるというふうに…。
Q:個人活動は報告しなくて勝手にやっていいですか(1日目)
A:
正会員・その年度の資格登録の更新ができていれば、個人活動は自由にできます。
ただしNPO法人に科せられた法律(NPO法)に準じた活動であることが前提。
また年に2回ほど個人活動報告と見合う寄附のお願いをしますので、できればそれにご協力をお願いします。
Q:完全呼吸法がわかりません(2日目)
A:
仰向けの状態で順番に呼吸していく事を意識して、再度行ってみましょう。
Q:肛門をしめる感覚がわかりづらいです(2日目)
A:
まずはお尻をしっかりとしめる事から力を入れていく感覚がつかめるようにする。
あぐらの状態でも肛門が閉められるように立った状態で少しずつ足を開いていきながら骨盤底筋を強化していくことも提案してみました。
Q:ろうそく瞑想などは普段のレッスンの最後に必ず行いますか(2日目)
A:
瞑想は普段のレッスンではシャバアーサナの時に身体を観察することや、ポーズの時に観察することや、呼吸法をしながら行ったりしているので、最後に必ずしないといけないというものではないです。
Q:仕事などでストレスを感じた時、心の持っていき方をどうすればいいですか(2日目)
A:
心の中のもやもやを観察して、自分で何か解決出来るものなら改善するようにし、自分ではどうにもならない事なら考える事を手放すようにする。
Q:体の状態を常に整えておくと、心の状態も乱れないということですか(2日目)
A:
はい、そうです。
インド5000年の智恵の中に心身の状態をコントロールする呼吸法があり、それを私達は健康活用法としてこの章で学びます。
近年科学的研究が進んでその効果が証明されていることが多くなっていますので統合医療の分野としてしっかりと覚えると役に立つと思います。
「氣」という考え方は東洋の概念ですが、心は氣と大きく関与し目に見える物質身の状態と同調している(一如)と考えられています。
しかし目に見えない領域である心をコントロールすることはなかなか難しく、そこで物質である体の状態を呼吸法で調氣することで心を支配しているホルモンや神経の働きをコントロールしていく、これがプラーナヤーマ~プラティヤハーラの段階の教えとなります。
日頃から身体を整えて氣を調え、呼吸を安定させることで生命の状態がより良く維持できるということなのです。
Q:瞑想をしていても、色々なことが浮かんできます(2日目)
A:
浮かんでくるのは当たり前です。ストレスが多いほど浮かんでくるものなので、否定せずその状態を受け入れましょう。
ただ、浮かんできたら決して囚われないことです。例えばスマホ画面をサッとスライドするように消し去りましょう。
浮かんでくることに囚われて考えだしたり、そこからストーリーを追いかけてしまうと思考脳が動いてしまいます。
じっと座ることで運動脳を停止させ、考え込まないことで思考脳を停止させ、「瞑想脳」にスイッチを入れるのが瞑想ですから、浮かび事(妄想)が湧くたびにどんどん消しましょう。
消す方法は「他に集中する」ことです。何かを観続ける、真言を唱え続ける、今の感覚に意識を向ける、そして、呼吸をしている状態に気づきを戻していくのです。
継続は力なりと言いますが、瞑想を続けるとやがて脳が落ち着きやすくなり、心の動きが停止する状態が起きてきます。
Q:30分の瞑想は難しいです(普段は10分ほど) 先生は、どうやっていますか(2日目)
A:
瞑想に基本、時間原則は無いと思っています。1分でも1時間でも、まずは自分が気持ち良い時間・環境で行う事です。
私が30分と申し上げたのは「坐禅」の例です。禅宗の坐禅は30分坐ったら次に歩行禅をし、再び30分坐ります。
瞑想には静禅と動禅がありますが気質的に体を動かす瞑想が合っている人もいますので、体を動かす瞑想体験をされてみてはいかがでしょう?
瞑想は「気づき」です。 そして気づく手法は世界中にあります。
龍村修先生の著書「瞑想100」をご紹介致しますので、是非熟読し、知識を深め、できそうなことから実践してみて下さい。
Q:P51(4)入浴後は分かるが、入浴前がNGなのは何故ですか(3日目)
A:
ヨガで血行が良くなった後すぐに入浴するのは、体に負担がかかるため。
Q:P52(5)結婚指輪など、普段外すことのないアクセサリーも外したほうが良いですか(3日目)
A:
スマートウォッチなどを常に装着している方も最近は多くいます。結婚指輪も無理に外す必要はないです。
当たって痛い場合や気になる時には外してください。
Q:胸の大きさの左右差は何か理由がありますか(4日目)
A:
胸の左右の高低差をみる時にはバストではなくチェストをみるので、バストの左右差はどんな理由があるのでしょう…
と皆で考えてみるにとどまりました。
※ヨガアドバイザーからのコメント
乳腺の発達(ホルモン分泌)の仕方や、脂肪の偏りなどで差が出ることがある。
また、心臓の機能が影響し、大きく育つ人もいる。
Q:修正法の動きで起き上がれませんでした。
起き上がれるようになりますか 腹筋が足りないのでしょうか(4日目)
A:
修正法は筋力アップして起き上がるのが目的ではありません。
やっていくうちに修正されて起き上がるようになるかもしれませんね。
5日目のロールプレイングに関して(4日目の説明時の質問)
Q:緊張しないようにするには
A:労宮のツボを押してみる。とにかく声に出して練習してみる。
Q:自分の先生の言い回しをコピーしても良いですか
A:良いなぁと思った言葉は使っていいと思います。
Q:どのように組み立てたら良いですか
A:例えばメインのポーズを決めてそれに対して修正する動きを入れて一通りやってみる。
Q.もしも教室で生徒さんが怪我をした場合はどう対処したら良いですか(5日目)
A:
今まで私たちがあった事例をお伝えしました。
・暑い日に教室に来るまでに熱中症のような症状(90代)。
盛岡市の事業で市役所職員(保健師)の方がいらしたので、対処をお願いした。
ご家族に連絡し、帰っていただいた。
・何度も手術歴のある方(80代)。午前中に多くの用事を済ませ、急いで午後の教室に参加。
1時間半のヨガ。最後のシャバアーサナ後に仰向けのまま目眩がする、と起きられなくなった。
教室を行っているセンターの職員に手伝ってもらい、救急車を呼んだ。
1人で教室を行っていると、どうしたら良いのか分からなくなってしまうかもしれないが、センター(公民館)に職員の方がいれば手伝ってもらう。
数年に一度は地域の消防組合が行っている普通救命講習に参加することをお勧めします。
※ヨガアドバイザーからのコメント
依頼されているクラスであろうが、個人が行うクラスであろうが、緊急対応マニュアルの存在は大事です。
指導者の責任・姿勢として、「安全」への準備をかかさないこと。
センター、世話役、ローテーション講師陣などと包括して取り組むことを怠らないで下さい。
Q.女性の先生でも、男性の生徒さんにも同じように指導されますか(5日目)
A:
教室の運営の仕方にもよりますが、基本的には同じように指導させて頂きます。
Q.修正法をどう入れたら良いか分かりません(5日目)
A:
今はテキストにあるポーズに対しての準備の修正から慣れていく方がいいと思います。
※ヨガアドバイザーからのコメント
あるポーズをする時にまずスタートの姿勢を観ます。
左右や前後の歪みがないか?じっくり観察してください。
観察する人は目視にて、また、観られる人は感覚の差などで把握しておきます。
主に開きの差、傾きの差、呼吸の状態などを観察すると良いです。
そして、テキストにある修正をしかけ、再チェックし、変化に気づいて下さい。
テキストの修正法は、積極的修正法と自然修正法しか紹介されていませんが、他に抵抗法を用いる消極的修正法や関連部位法などがありますよね。
これらに関しては、10月に定例開催されるトレーニングキャンプにて当団体のヨガアドバイザー龍村修先生の指導から学ぶことが可能です。是非ご参加ください。